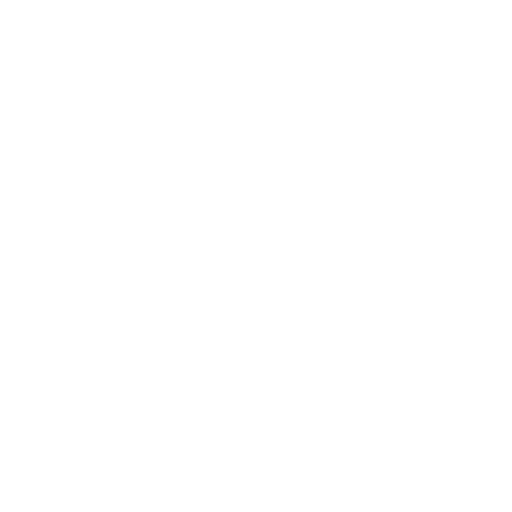第1条 身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体抑制(拘束)は、人間としての尊厳の侵害、QOLの低下や心理状態を悪化させるため、人権擁護の観点から適切といえない。
そのため、患者の生命の危機と身体的損傷を防ぐ目的で他に手段がない場合以外に行うべきではない。
しかし、急性期医療の中で治療を中心とした疾病管理が優先され、患者の安全確保を 目的に、やむを得ず抑制(拘束)しなければならない事例も少なくない。私たちは「抑制(拘束)をしないための具体的なケア」を追求しつつ不要な抑制(拘束)を少なくするために、十分な検討と患者理解を行い、根拠に基づいた安全で効果的な最小限の抑制(拘束)を実施しなければならない。
第2条 身体的拘束最小化に向けての基本方針
私たちは、患者の基本的人権を尊重して、生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない。
この指針でいう抑制(拘束)とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの 用具を使用して、一時的に当該 患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
- 緊急やむを得ない状態とは、以下の 3つの要件をすべて満たした状態である。
・切迫性
患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる危険性が著しく高いこと
・非代替性
身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法がないこと
・一時性
身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること - 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、「医療安全管理マニュアル第3章:身体抑制(拘束)」に準じて行う。
- 身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為は最小限とする。
- 鎮静を目的とした薬物については適正使用に努め、患者に不利益が生じないように使用する。使用については、患者・家族等に説明を行う。
第3条 身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」という)を設置する。
1.チームの構成
チームは、専任の医師及び専任の看護師、看護部、薬剤師、リハビリテーション科、メディカルソーシャルワーカー、事務員等のメンバーをもって構成する。
2.チームの役割
- 身体抑制(拘束)の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
- 身体抑制(拘束)実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
- 定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
- 身体抑制(拘束)最小化のための職員研修を開催し、記録をする。
第4条 身体的拘束最小化のための研修
入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を行う。
- 定期的な教育研修(年1回)実施(新規採用時にも必ず実施する)
- その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
第5条 身体的拘束を行う場合の対応
- 医師・看護師は、アセスメントを行い、身体抑制(拘束)をするべきか否かを判断し、緊急やむを得ない理由を記録に残す。
- 身体抑制(拘束)が必要と判断された場合、医師は、「やむを得ない身体抑制(拘束)に関する説明書及び同意書」の必要な個所を記入し、患者・家族(または代理人)にその必要性を十分に説明し、承諾を得たのち、身体抑制(拘束)開始の指示を入力する。
- 身体抑制(拘束)の同意が得られない場合は、ご家族に付き添って頂くなどの協力を得る。
- 身体抑制(拘束)回避へのアプローチ
① 身体抑制(拘束)が必要なのかを、医師・看護師と共に毎日アセスメントし、評価し記録に残す。
② 最低週1回は、医師・看護師を含む多職種間で必ずカンファレンスを行い、身体抑制(拘束)の継続・変更・解除検討し、記録に残す。 - 観察について
看護師は原則として、身体抑制(拘束)開始15分後、その後は2時間毎に、抑制(拘束)部位の皮膚の状態、抑制(拘束)による二次的障害、精神状態について観察し、身体抑制チェックシートに入力する。 - 病棟管理日誌記載について
各病棟にて、身体抑制(拘束)中の患者を把握するため、病棟管理日誌の備考欄に「身体抑制(拘束)患者:〇〇(抑制器具種類名)」と記載する。
第6条 多職種による安全な身体的拘束の実施及び解除に向けた活動
- 看護師は、身体抑制(拘束)開始後から毎日アセスメントを実施する。
- 医師、看護師は、共に毎日評価、1回/週程度多職種を交えてカンファレンス等で身体抑制(拘束)継続についてのアセスメント・カンファレンスした内容を カルテに記録する。
- 身体抑制(拘束)の必要性がないと判断された場合に、それに伴う危険性の有無を評価し、カルテに記録する。
- 医師の指示の下、身体抑制(拘束)を解除する。
第7条 当該指針の閲覧に関して
本指針は、当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者様、ご家族等が閲覧できるようにする。
(附則)この指針は、令和7年1月1日から施行する。